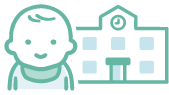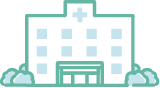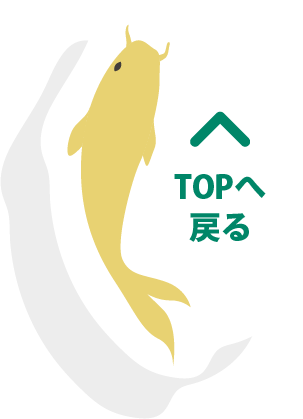本文
介護認定を受けるためには
介護認定の手続きなどについてのご案内です。
要介護認定の申請
介護保険からサービスを受けるためには、日常生活において介護が必要な状態にあるかどうかの認定を受ける必要があります。
申請できる方
- 1号被保険者(65歳以上の方)
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)で下記の特定疾病に該当する方
- 初老期における認知症(診断名/アルツハイマー病・血管性認知症など)
- 脳血管疾患(診断名/脳出血・脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症(診断名/筋萎縮性側索硬化症)
- パーキンソン病(診断名/パーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症(診断名/脊髄小脳変性症)
- シャイ・ドレーガー症候群(診断名/シャイ・ドレーガー症候群)
- 糖尿病性疾患(診断名/糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害)
- 閉塞性動脈硬化症(診断名/閉塞性動脈硬化症)
- 慢性閉塞性肺疾患(診断名/肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎)
- 著しい変形を伴う変形性関節症(診断名/両変形性膝関節症・両変形性股関節症)
- 慢性関節リウマチ(診断名/慢性関節リウマチ)
- 後縦靱帯骨化症(診断名/後縦靱帯骨化症)
- 脊柱管狭窄症(診断名/腰部脊柱管狭窄症・頚部脊柱管狭窄症)
- 骨折を伴う骨粗しょう症(診断名/脊椎圧迫骨折・大腿骨頚部骨折・転子部骨折)
- 早老症(診断名/ウェルナー症候群)
- がん末期(診断名/がん末期)
申請手続
本人または親族の方から市(福祉課)の窓口で手続きを行っていただきます。その際、介護保険被保険者証をお持ちください。
(なお、利用している居宅介護支援事業所や介護保険施設に手続きを代行してもらうこともできます。)
介護保険認定申請書(裏面:介護認定調査連絡票)と記載例は下記<関連リンク>からダウンロードできます。
申請から要介護認定までの流れ
1. 申請
市(福祉課)に申請書を提出していただきます。
2. 訪問調査
訪問調査員がご自宅を訪問し、対象者の心身の状態などについて調査を行います。
3. 主治医意見書
かかりつけ医より、医学的な面からの心身の状態などを意見書として提出してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、申請時にご相談ください。
4. 介護認定審査会
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、専門家による審査が行われ、要介護度が判定されます。
5. 認定結果の通知
介護認定審査会にて判定された結果を市が認定し、認定結果(要介護度、認定有効期間など)を記載した介護保険被保険者証と結果通知を郵送します。
更新申請の認定有効期間内の延期通知省略について
介護保険法では、申請から30日以内に認定ができない場合、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないとされています。
このうち更新申請については、有効期間内に認定ができる場合であれば、申請から30日を超えて認定を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。
本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に認定ができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解いただきますようお願いします。
認定申請中に被保険者が亡くなられた場合
要介護認定申請中に被保険者が亡くなられた場合は、申請区分及び審査判定資料の進捗状況により、次のとおり取り扱います。
- 認定調査前に亡くなられた場合は審査判定に必要な資料が揃わないため認定手続きを行うことができません。→認定を却下します。
- 更新申請中で、以前の認定の有効期間内に亡くなられた場合は、有効開始日時点で資格喪失されているため、認定できません。→認定を却下します。
- 認定調査が済んでおり、主治医意見書の提出があった場合は認定手続きを継続します。→認定結果確認後、認定結果を通知します。
- 介護保険認定申請書(裏面:介護認定調査連絡票) [Wordファイル/86KB](可能であれば両面印刷を行ってください。)
- 介護保険認定申請書(裏面:介護認定調査連絡票)記載例 [PDFファイル/277KB]