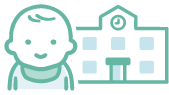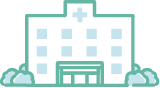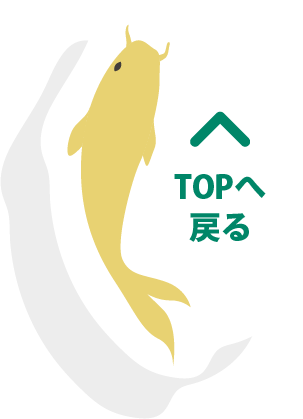本文
予防接種について
赤ちゃんの免疫は、生後数か月で自然に失われます。
予防接種を打つことで、病気から体を守り、万が一病気にかかっても症状を軽くするための免疫を準備することができます。
お子さんの出生後に、予防接種についての冊子「予防接種と子どもの健康」をお渡ししていますので、よくお読みいただき、予防接種の有効性と安全性についてご理解いただいてから、お子さんの体調が良いときに接種を受けましょう。
面倒な記入をスマホで簡単に!予防接種予診票のデジタル化
小千谷市では、マイナンバーカードを使ったデジタル予診票を導入しています。
マイナポータルから予診票の入力や接種結果の確認ができます。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
予防接種を受けるには
個別接種になります。市内の委託医療機関で実施します。
事前に接種医療機関へ電話などで予約をしてください。
接種費用
無料 ※ただし、対象年齢を過ぎると全額自己負担となります。
お持ちいただくもの
- 母子健康手帳
- 予防接種予診票
(出生届時に予防接種予診票のつづりをお渡ししています。接種を受ける予診票に必要事項を記入のうえお持ちください)
※デジタル予診票を利用する場合は、「マイナンバーカード」と「母子健康手帳」が必要です。
定期予防接種の種類・回数など
|
予防接種の種類 |
回数 |
対象年齢 |
|---|---|---|
| B型肝炎 | 3回 |
1歳未満 【標準的な接種方法】 27日以上の間隔で2回目までを接種し、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種。 |
|
小児用肺炎球菌 |
4回(初回3回、追加1回) *初回接種月齢・年齢で接種回数が異なります。 |
生後2か月~5歳未満 【標準的な接種方法】 ●追加:初回終了後、60日以上の間隔をおいて生後12か月から生後15か月に至るまでの間に1回接種。 |
|
ロタ(ロタリックス) |
2回 |
生後6週~24週まで 【標準的な接種方法】 |
|
ロタ(ロタテック) |
3回 |
生後6週~32週まで 【標準的な接種方法】 |
|
5種混合ワクチン (ヒブ、ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ) |
4回(初回3回、追加1回)
|
生後2か月~7歳6か月未満 【標準的な接種方法】 ●初回:生後2か月から生後6か月までの間に20日以上の間隔をおいて3回接種。 ●追加:初回終了後6か月から18か月までの間隔をおいて接種。 |
|
ヒブ *令和6年4月1日から5種混合ワクチンに含まれます。 *ヒブワクチンで接種を開始した場合は、原則同じワクチンで接種を完了してください。 |
4回(初回3回、追加1回) *初回接種月齢・年齢で接種回数が異なります。 |
生後2か月~5歳未満 【標準的な接種方法】 ●初回:生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始。4週間から8週間の間隔で3回目までを接種。 ●追加:初回終了後7か月から13か月の間隔をおいて1回接種。 |
|
4種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ) *令和6年4月1日から五種混合ワクチン(四種混合にヒブワクチンを加えたワクチン)が定期接種となったことにより、四種混合ワクチンの販売が終了となりました。四種混合ワクチンを接種できるのは、ワクチンの在庫がある間のみとなります。四種混合とヒブワクチンの接種回数が同じ方は、五種混合ワクチンに切り替えて接種することができます。 |
4回(初回3回、追加1回) |
生後2か月~7歳6か月未満 【標準的な接種方法】 ●1期初回:生後2か月から12か月の間に20日~56日の間隔をおいて3回接種。 ●1期追加:初回接種終了後、12か月~18か月までの間隔をおいて1回接種。 |
|
BCG |
1回 |
生後直後~1歳未満 【標準的な接種方法】 生後5か月~生後8か月に至るまでの間に接種。 |
|
水痘 |
2回 |
生後12か月~36か月未満 【標準的な接種方法】 生後12か月から15か月に至るまでに1回接種し、その後6か月から12か月の間隔をおいて1回接種。 |
|
麻しん風しん(第1期) *令和6年度に満2歳を迎えた児(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの児)でワクチン不足等により対象年齢内に接種ができなかった児には、令和9年3月31日まで経過措置が設けられることになりました。 |
1回 |
1歳~2歳未満 【標準的な接種方法】 生後12か月から24か月に至るまでに1回接種。 |
|
麻しん風しん(第2期) *令和6年度の年長児(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの児)でワクチン不足等により対象年齢内に接種ができなかった児には、令和9年3月31日まで経過措置が設けられることになりました。 |
1回 | 満5歳~7歳未満で小学校に就学する前の1年間 |
| 日本脳炎(第1期) | 3回 (初回2回、追加1回) |
生後6か月~7歳6か月未満 《特例措置》 |
| 日本脳炎(第2期) | 1回 |
9歳以上~13歳未満 《特例措置》 |
| 2種混合(ジフテリア・破傷風) | 1回 |
11歳~13歳未満 【標準的な接種方法】 生後11歳から12歳に至るまでの間に接種。 |
| 子宮頸がん予防ワクチン |
2~3回 *初回接種年齢・ワクチンで接種回数が異なります。 |
小学6年~高校1年生相当の年齢の女子 ワクチンはサーバリックス、ガーダシル、シルガード9の3種類があります。 【標準的な接種方法】 |
予防接種を実施する医療機関
予防接種を実施する市内医療機関の一覧をPDFで掲載しています。
各医療機関によって接種できる種類が異なりますので、ご確認の上、接種を希望する日の3日前までに電話で申し込んでください。
新潟県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合
里帰り出産や通学等でやむをえず新潟県外で定期予防接種を希望する方は事前に健康・子育て応援課へご相談ください。※国外の医療機関で接種した場合は対象となりません。
予防接種法に基づき、県外の医療機関で予防接種を受ける際、その実施責任が小千谷市長にあることを明確にした書類である「予防接種実施依頼書」を発行します。この書類がないと、健康被害を生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。
1.事前手続き
(1)滞在先の市区町村予防接種担当課に次のことを確認し、その後小千谷市へ連絡してください。
- 県外の方の予防接種を受け入れているか
- 予防接種実施依頼書の依頼先は、自治体の長(市区町村長)か医療機関の長か。
(2)予防接種実施依頼書交付申請書に必要事項を記入し、小千谷市に提出してください。後日、予防接種実施依頼書をご希望の送付先に郵送します。
※依頼書を発行するまでに数日かかりますので早めに手続きをお願いします。
申請書(予防接種実施依頼書交付申請書) [PDFファイル/87KB]はこちら
2.予防接種を受ける
郵送された「予防接種実施依頼書」を医療機関に提出し、接種を受けてください。
※接種費用はいったん全額支払っていただき、払い戻しの手続き(予防接種助成金交付申請)を行う事で接種費用の全額または一部を払い戻します。
3.予防接種費用払い戻しの手続きをする(予防接種助成金交付申請)
「予防接種実施依頼書」により、予防接種を自費で受けた場合、その費用の全額または一部を助成します。接種終了後、6か月以内に申請してください。
※国外の医療機関で接種した場合は対象となりません。
お持ちいただくもの
- 予防接種助成金交付申請書 [PDFファイル/141KB]
- 接種費用の支払いを証明する書類の原本(接種年月日、ワクチンの種類、ワクチン毎の接種費用、医療機関名がわかるもの。なお、内訳の記載がない場合は、明細書もご提出ください。)
- 接種した予防接種の予診票の写し(接種した医療機関から受け取ってください)
- 母子健康手帳または医療機関発行の予防接種済であることを証する書類
- 振込先金融機関の通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できる書類)
注意する点
- 助成する期間は、予防接種を受けた月の末日から6か月以内となります。
- 接種料金は医療機関によって異なる場合があるため、全額助成できない場合があります。
- 各予防接種の対象年齢を過ぎてから受けたものは助成の対象となりません。
<関連リンク>