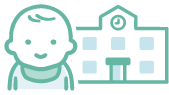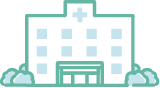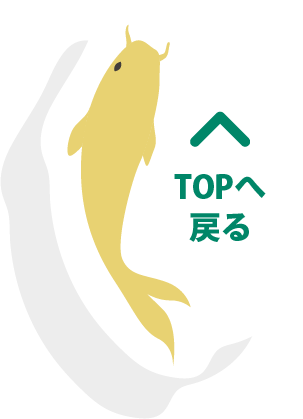本文
魚沼神社太太神楽(うおぬまじんじゃだいだいかぐら)
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
魚沼神社太太神楽の由来
魚沼神社の太太神楽は、江戸時代に現在の柏崎市北条(きたじょう)の御嶋石部神社(みしまいそべじんじゃ)から、神楽面や舞人を借りて実施したことが始まりとされています。庭清舞(にわきまい)や草薙舞(くさなぎまい)など十二演目あり、古事記などの伝説を題材に、横笛・太鼓の伴奏にあわせて、物語を舞によって演じます。
太平洋戦争の激化とともに中断しましたが、戦後まもなくの昭和23(1948)年、27(1952)年に「太太神楽奉加帳」が回されており、復活したことが分かります。その後、高度経済成長期に再び途絶えましたが、昭和52(1977)年に魚沼神社太太神楽保存会が結成され、復活上演し今日に至っています。
現在は、毎年8月15日、16日の魚沼神社例大祭で奉納されるため、7月になると練習が本格化し、笛の音が町内に響き渡ります。
舞や囃子は、地域の小学生から社会人の若い世代によって行われています。例大祭がお盆の期間でもあり、市外から帰省して参加する
会員もいるなど、活発に活動しています。
文化財指定日 2014年3月24日