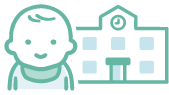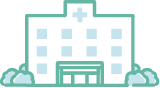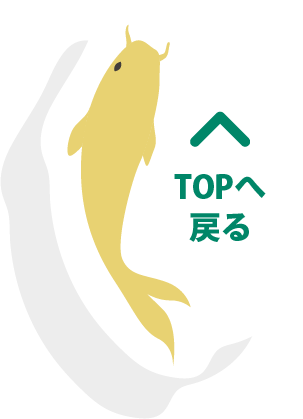本文
大の釈迦踊(だいのさかおどり)
大の釈迦踊は、中世の仏教興隆期に大坂方面で始まったものが、近世の小千谷縮商人などによって伝えられたといわれています。念仏踊としては、市内に伝わる唯一のものです。
真人町の円蔵寺には、泡観音(あわかんのん)と呼ばれる観音像が安置されています。この像は、洪水で信濃川から流れてきたと伝えられ、川から上がったとされる8月17日を年に一度の開帳日としています。大の釈迦踊も、泡観音が川から上がったことを機に始まったともいわれ、同日に寺の前庭で踊られています。
この踊り最大の特徴は、笛や太鼓などの楽器を使用せず、音頭取りと踊り手の囃子だけで時計まわりに踊られることです。魚沼市堀之内に伝わる「大の阪」と名称は似ているものの、堀之内では笛太鼓を使用すること、踊りや唄がいずれも大きく異なることから、起源の違うものと推定できます。また、十日町市には歌詞が類似した「大の釈迦」が伝わっており、こちらは関連性がうかがえます。
文化財指定日 1977年4月1日


| 所在地 | 小千谷市真人町乙661-1 | 地図 |
| アクセス | 関越自動車道越後川口インターから車で15分 |
大の釈迦踊の唄(一部)
だいしょしゃー ほい しゃーほいよー ほーい
ほいよー ほうほうーっ ほうほう
ねぇー さは すいやきりゃー ほうほう
ねぇー さは すいやー さあはんよー
セェーエホ セェーホウォ ホラ コレモセェ
セェーホウ センガイヤーデ コレモセェー ホウホウ
セェホラ セェホウ スイヨノホウ セェーホノセエ
皆様その声さまさずに
ヨイヤラシャー ヨイヤラシャー
はやしあるならまた語る
ヨイヤラシャー ヨイヤラシャー
極楽の 極楽の
ヨイヤラシャー ヨイヤラシャー
前の榎になにが成る
ヨイヤラシャー ヨイヤラシャー
南無阿弥陀仏と後生の実がなる
よーおいと ほんなぁー
シェーホウ センガイヤーデ コレモシェー