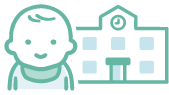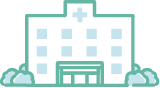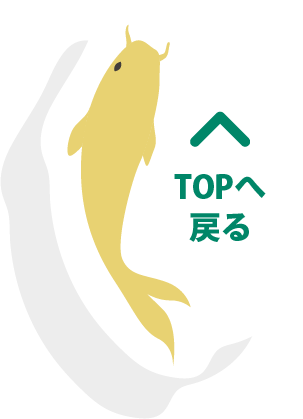本文
薭生(ひう)城跡
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
薭生城は薭生山の頂上付近(標高258メートル)、三国街道と信濃川を見下ろす、陸運・舟運の要所に位置します。
築城年代は不明ですが、当初は薭生氏が居城し、大永3(1523)年には平子右馬允(たいらこうまのじょう)が居城としたといわれています。上杉謙信没後に起きた後継者争いの御館の乱で平子氏は景虎方についたため、天正7(1579)年、景勝方に攻められ落城したといわれています。慶長5(1600)年の上杉家遺民一揆では、五智院(ごちいん)の僧、海龍が率いる3800人が立籠もったともいわれています。
頂上付近にある主郭部は、外周を急峻な切岸により堅固に仕上げています。このほか堀切や「乱穴」(らんあな)と呼ばれる横穴などの防衛設備が見られます。中でもこの城の最大の特徴は放射状に連続して掘削された竪堀で、現在でも正確な数が把握できないほどです。
頂上付近には「蔵屋敷」「道場屋敷」、中腹には「水源山殿入沢」「車落とし」「中屋敷」など城に関連する地名が多く見られます。
文化財指定日 1972年4月1日