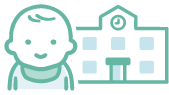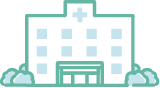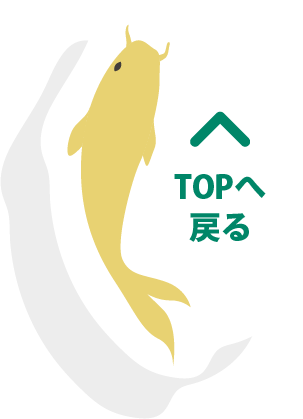本文
豊年獅子舞(ほうねんししまい)
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
豊年獅子舞は、下タ町(したまち、現・元町)にあった諏訪神社の祭礼で舞われていました。諏訪神社が明治42(1909)年10月に本町の二荒(にっこう)神社に合祀(ごうし)されてからは、毎年7月の二荒神社の祭礼で舞われています。
この獅子舞についての来歴は明らかではありませんが、江戸時代後期頃に、小千谷縮による交流を通して伝来したといわれており、最も古い記録は天保12(1841)年の資料が残っています。
山の神(天狗、てんぐ )を主体にして、日輪を象徴した日傘を中心に、牡獅子(おじし)・牝獅子(めじし)・仔獅子(こじし)の三頭が舞うもので、囃子(はやし) には、太鼓・笛・簓(ささら)の楽器が用いられましたが、簓だけは現在使用されていません。
踊りは、「岡崎の舞」「かくだいの舞」「かくすけの舞」「仕組の舞」「橋渡の舞」「蔦つた渡の舞」が伝承されています。
囃子の途中で歌われる歌詞は、関東から東北地方に分布する三匹獅子と同系のものだともいわれています。
文化財指定日 1972年4月1日

| 所在地 | 小千谷市本町1丁目5 | 地図 |
| アクセス | 関越自動車道小千谷インターから車で3分 |