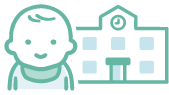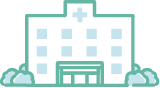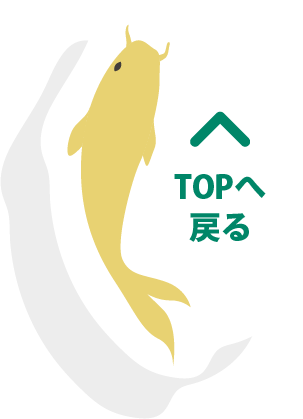本文
百塚
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
百塚は三仏生集落の西側にあり、千谷との境から高梨方面に約1キロにわたって塚が直線上かつ規則的に並んでいます。塚の多くは円
形で、一基のおよその大きさは、底径が約4メートル、高さが約1.5メートルです。現在141基が確認できますが、以前は150基以上あったといわれています。
塚が作られた年代や、由来についての記録は見つかっていませんが、多くの伝説や伝承が残されています。
例えば、朝日長者から財宝を隠すために夕日長者が塚を造り、盗掘されないよう同じような塚をいくつも造ったという「夕日長者」伝説が知られています。また、天変地異から免れるための祈願を込めて造られたという説や、昔の街道に沿って造られた道標であるという説もあります。他地域の事例では、大きな合戦があった地域にこのような塚群が見られることもあり、記録には残らない武士の合戦跡である可能性も示唆されます。
三仏生では、天保10年代(1839年前後)から塚群の保存活動が始まったといわれ、江戸時代後期の弘化4(1847)年には秩父三十四、坂東三十三、西国三十三、越後三十三観音の各札所の石仏が塚の上に立てられました。
春は桜の名所としても知られ、地元の人々から大切に保存されています。
文化財指定日 1990年7月20日