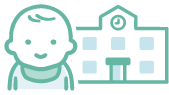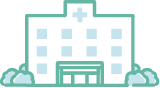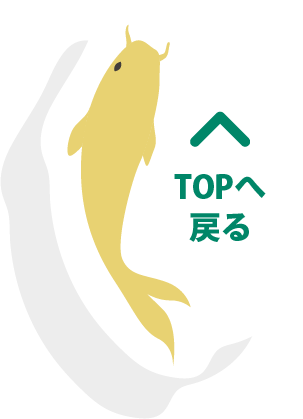本文
清水上(しみずのうえ)遺跡(三仏生(さんぶしょう)遺跡)
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
清水上遺跡は、今から約四千~三千年前の縄文時代後期の遺跡です。通称「たかはつら」といわれる、三仏生(さんぶしょう)集落の中でも信濃川により近い段丘一帯が遺跡として登録されています。
この周辺では、現在でも段丘崖(だんきゅうがい)から清水が湧(わ)き出しており、「清水上」という地名もここからきたものと推定できます。
この遺跡周辺は、大正時代初期に開墾されるまでは雑木林でしたが、この開墾の際、表土中から土器や石器が多く出土したという記録が残っています。当初は、地元収集家の細貝嘉明氏がこのことに注目していました。その後、長岡市関原の近藤勘治郎氏が数度にわたり探査収集を行って学会に報告したことで、この遺跡が考古学会において脚光をあびることとなりました。昭和30(1955)年8月には発掘調査が行われ、報告書が刊行されています。
この遺跡の代表的な土器は、縄文時代後期の磨消縄文と呼ばれる形式で、「三仏生式」と呼ばれています。
文化財指定日 1972年4月1日