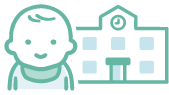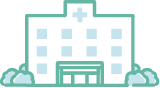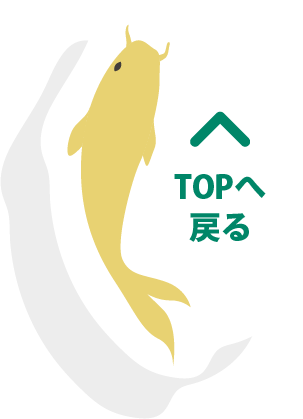本文
高梨城本丸跡
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
高梨城は、信濃川に形成された低位段丘の突端部に築かれた平山城(ひらやまじろ、平地にある丘陵などに造られた城)です。文明年間(1469~1487年)は長尾氏(ながおし)の居城で、その後、長尾氏の家臣、高梨源五郎頼春の居城になったことや、永禄年間(1568年前後)に高梨修理亮守将が居城していたなどといわれていますが、いずれも江戸時代の記録や伝承によるものであり、当時の明確な文書などの記録はほとんど見つかっていません。御館(おたて)の乱の後、天正7(1579)年に廃城になったといわれています。
段丘面の平坦な地形ですが、段丘崖を天然の切岸(きりぎし)とし、さらに空堀(からぼり)により敵の侵入を防ぐ防衛設備としています。この城最大の特徴は、郭を囲い込む土塁(土を積み上げて築いた防壁)で、明治時代以降の農耕などの影響で削られた部分も多いですが、主郭(しゅかく)部の外周には当時の普請の跡も観察することができます。
文化財指定日 1981年8月22日
 地元では高梨城主の墳墓と伝えられる
地元では高梨城主の墳墓と伝えられる