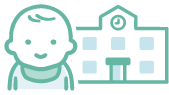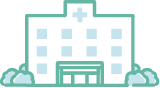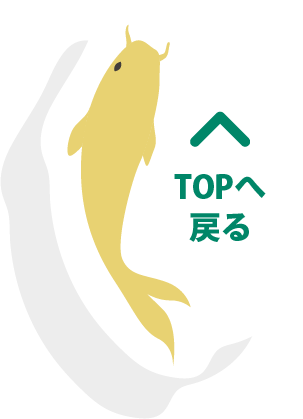本文
時水(ときみず)城跡
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
時水城は、小千谷市と旧小国町に連なる城山(じょうやま、標高384メートル)山頂と、東方に分岐(ぶんき)した尾根に築かれた山城です。
南北朝時代は新田氏家臣の小国氏、正平年間(1346~1370年)からは上杉氏の家臣、曽根氏が支配したとされています。その後、曽根宗能が上杉謙信に叛(そむ)き、薭生(ひう)城主平子氏(たいらこし)の攻撃を受けて落城したといわれていますが、いずれも江戸時代の記録や伝承によるもので、当時の確かな文書などは見つかっていません。
城山(通称夏城)の主郭部(しゅかくぶ)最大の特徴は、「階段状の切岸」を外周部に数多くめぐらして防衛とするとともに、山城そのものの崩落(ほうらく)を防いでいるところです。
分岐した尾根の山城(通称冬城)は冬期作戦のために築かれたと伝えられていますが、現在では山頂の主郭部への進軍経路を遮断する
砦の一つと考えられています。
付近には「舟くぼ」「鐘塚」「馬場清水」など当時の様子を示す地名が残っています。現在はハイキングコースとして親しまれており、
天気の良い日は頂上から佐渡島を望める絶景ポイントです。
文化財指定日 1972年4月1日