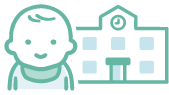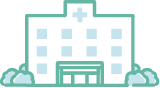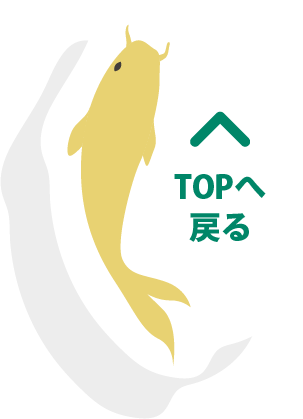本文
牛の角突き(うしのつのつき)
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
牛の角突きは、小千谷市東山、長岡市山古志、魚沼市広神にまたがる二十村郷(にじゅうむらごう)で始まった習俗です。
一説には岩手県南部地方から鉄を運んできた荷役(にえき)用の牛を買い、農耕に使うかたわら角突きを始めたといわれています。江戸時代のベストセラー曲亭馬琴(きょくていばきん)の『南総里見八犬伝』(なんそうさとみはっけんでん)の中には、当地の牛の角突きに関する記述があります。
二十村郷の牛の角突きは、五穀成就や安全祈願、神への感謝を込めた神事としての役割もあり、牛舎祭り、牛見祝、出陣、引き出し、勝ち祝、面綱綯(おもづなな)い等の行事で構成されています。
闘牛場では、勢子の「ヨシター」の掛け声が牛に勢いをかけます。
国内各地の闘牛の中で、唯一勝ち負けをつけず、引き分けを原則とすることが大きな特徴です。
牛飼いはこの日のために、牛を家族のように育て、成長を慶び、技を楽しむという、牛・牛飼い・地域が一体となった習俗です。
また、「木牛」という牛の角突きにちなんだ郷土玩具もあり、現在も東山地域ではその製作技術が大切に伝わっています。
文化財指定日 1978年5月22日


| 所在地 | 小千谷市大字小栗山 | 地図 |
| アクセス | 関越自動車道小千谷インターから車で16分 |
<関連リンク>