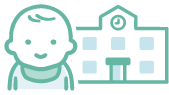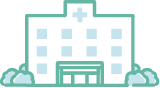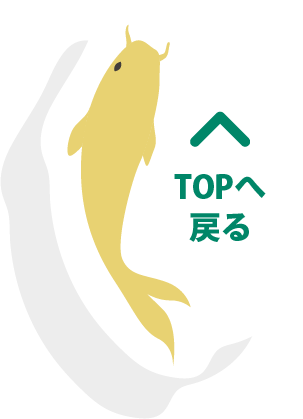本文
宇都宮神社鰐口(うつのみやじんじゃわにぐち)
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
鰐口とは、寺や神社の軒先に吊るされ、参拝者が打ち鳴らし来意を告げるための道具です。
事代主命(ことしろぬしのみこと)を御祭神とする藪川(やぶかわ)の宇都宮神社は、上弥彦社(現・魚沼神社)の十八末社に数えられています。宇都宮神社に伝わる鰐口は鋳銅製で、総径33センチメートル、鼓面径29.9センチメートル、鼓厚10.9センチメートル、肩厚6.5センチメートルです。中心部の撞座(つきざ)中央には蓮華(れんげ)の文様が施されています。圏線により外区・内区・撞座区にわかれていて、耳は両面鋳造です。
正面外区および内区に刻まれた銘文から、永享10(1438)年に、吉谷村の西片弥三郎光行が宇都宮神社に奉納したということが分かります。なお、西片弥三郎光行は、魚沼神社の鰐口を奉納した人物でもあります。
【正面外区および内区銘文】
宇都宮鰐口旦那平朝臣西片弥三郎光行願主 越後国魚沼郡内吉谷村藪河住人惣大宮司等 永享十年戊午七月中旬九日大工道久禅 敬白
文化財指定日 1983年3月25日