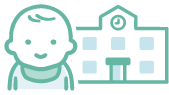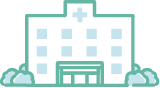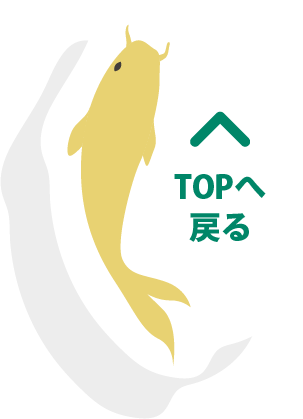本文
巫女爺人形(みこじいにんぎょう)操り
屋台人形巫女爺(やたいにんぎょうみこじい)
巫女爺人形操りは横町(よこまち、現・平成町)から周辺の地域に広まり、現在では小千谷市四団体と長岡市八団体、併せて十二団体が継承している、地域の枠を越えた独特な文化財です。
「巫女爺人形を操る」という点は共通ですが、歌曲・囃子(はやし) 、人形の形や表情、屋台の構造から継承の方法にいたるまで地域ごとに個性があります。いずれの地域でも名前は「巫女爺」ですが、読み方は「ミコジイ」、「メッコンジサ」、「ミコジサ」と様々です。
文化財指定日 2008年3月25日
横町巫女爺
横町の巫女爺は、江戸時代に風長(かざちょう)という店に滞在した「人形つかい」が、宿賃の不足分として置いていった爺(ジサ)の頭に衣装を着けて踊らせたのが始まりといわれています。当初は爺だけでしたが、一人では寂しいだろうと巫女(アネサ)が作られ、爺と巫女一対で踊らせるようになったそうです。
歌曲は「広大寺」「品玉」など全部で十曲あり、囃子は太鼓・三味線・笛・銅・拍子で構成されます。
米沢の俳人・遅日庵が、文化元(1804)年に記した『小千谷行日記』には二荒神社祭礼の様子が紹介されており、この中で「南京あやつり」と紹介されているものが、横町の巫女爺であると推定されます。



| 所在地 | 小千谷市本町1丁目(二荒神社・祭礼のみ) | 地図 |
| アクセス | 関越自動車道小千谷インターから車で3分 |
三仏生巫女爺(さんぶしょうみこじい)
三仏生の巫女爺は、江戸時代後期に始まったといわれており、人形や巫女の作りは横町のものとよく似ています。現在行われている巫女爺は、長らく途絶えていたものを、昭和47(1972)年に町内の有志が復活させたものです。昭和53(1978)年には巫女爺人形の本格的な復元修理を行い、以来地域行事に欠かせない大切な伝統民俗芸能として親しまれています。
演目は「広大寺」「おけさ」「すがらき」「巫女舞」の4曲です。上演で用いられる屋台が二階作りになっており、立ち人形の巫女を一
階から操作するために舞台が高く作られているのが特徴です。
 三仏生の巫女爺と屋台
三仏生の巫女爺と屋台
 巫女爺のからくり
巫女爺のからくり
千谷巫女爺(ちやみこじい)
千谷の巫女爺は、爺の人形のみ伝えられています。大正2(1913)年に、大正天皇即位記念で上演されたのを最後に、一度は途絶えたといわれています。昭和56(1981)年に、渡辺長右衛門氏宅から一体の巫女爺人形が発見され、東京国立博物館の鑑定で江戸時代後期のものであることが分かりました。同博物館の仏像修理室で修理を行うとともに、住民有志による保存会が結成され、横町巫女爺の指導を受けて昭和58(1983)年から上演が復活しました。
二人の人間が椅子に腰掛けて、一体の爺を操るのが特徴です。

 千谷の巫女爺はジサのみで上演されます
千谷の巫女爺はジサのみで上演されます
片貝巫女爺
片貝の巫女爺は、元治元(1864)年に神明社が再建された時、奉納芸として横町から伝えられたのが起源といわれています。神明社のほか、薬師堂、八幡社、秋祭りの帰り屋台などで上演されてきましたが、昭和48(1973)年を最後に途絶えたそうです。
しかし、平成2(1990)年の「片貝伝統芸能保存会」発足をきっかけに巫女爺の修復が始まり、平成7(1995)年に復活上演を行ってからは、町内の行事やお祭りの際に上演されています。また、巫女爺子ども教室など、後世に残す活動も続けています。


 子供巫女爺教室の様子
子供巫女爺教室の様子